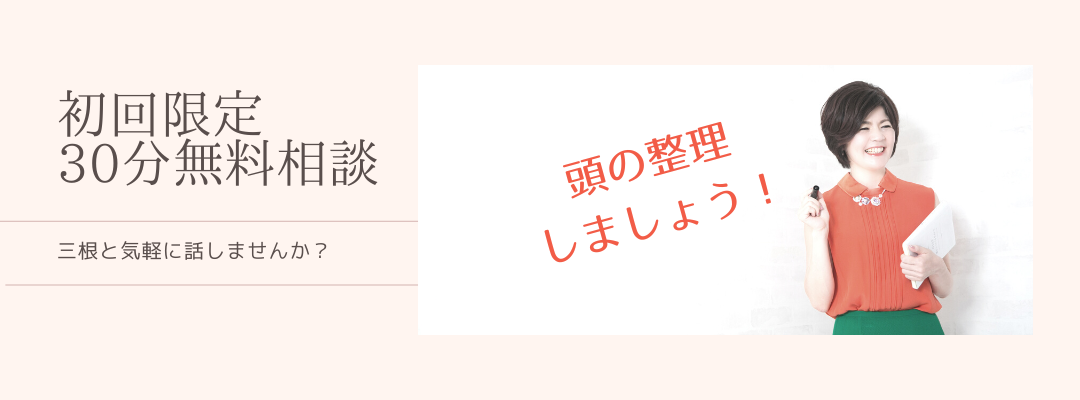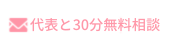お盆休みに気づいた、AIを「遊びながら」学ぶ力
2025/08/16お盆休みは、佐賀の実家に帰省してきました。
中学生の甥っ子と小学生の姪っ子がいて、帰るたびに会えるのが私の密かな楽しみです。
最近の子どもたちは学校でパソコンの授業もあり、私がパソコンで仕事をしていると
「なにしてるの?」
と興味津々で覗いてきます。
そこで今回は、少しだけAIの世界を体験してもらうことにしました。
遊び心から始まる学び
子どもたちに人気のアニメといえば「鬼滅の刃」や「推しの子」。
「自分の写真を鬼滅の刃風にして!」
「推しの子風に!」
とリクエストしながら、写真をイラスト風に変換するAIツールを楽しんでいました。
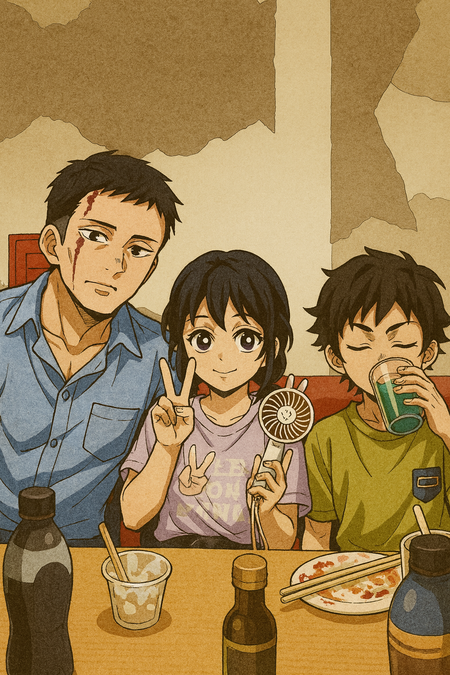
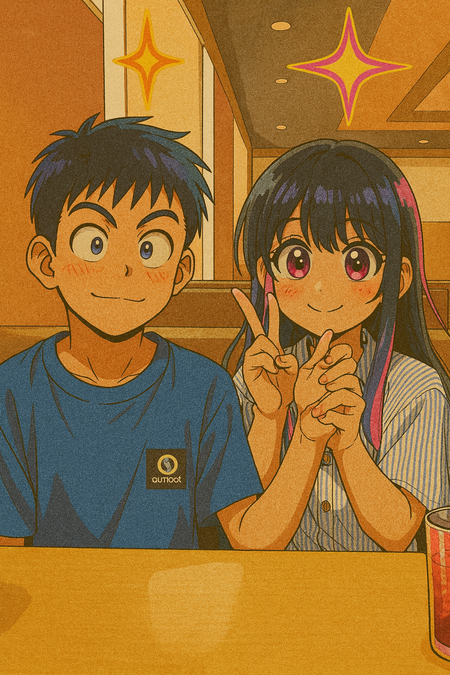
最初は面白がっていただけだったのに、慣れてくると
「この男の子が戦っている絵を描いてください」
と、どんどん具体的な指示ができるように。
その姿を見て、「まずは“遊び”から入って感覚的に慣れる」ことが、AIを使いこなす第一歩なんだなと改めて感じました。
思い出もAIが引き出してくれる
甥っ子と話しているとき、ふと彼の財布から古いレシートが出てきました。
「これ、何を買った時のだったっけ?」
と首をかしげていたので、
「AIに聞いてみようよ」
と提案。
レシートを読み込ませると、旅行中に買ったお菓子だと表示されました。
すると甥っ子も「あ、そうだった!」と思い出して、旅の話に花が咲きました。
単なるデータの処理に留まらず、AIは記憶を呼び起こすきっかけにもなるのだと気づいた瞬間でした。
経営にも通じる感覚
子どもたちと一緒にAIを触りながら思ったのは、「楽しみながら慣れる」
ことの大切さです。
経営者にとってもAIはもはや避けて通れない存在ですが、最初から「仕事に役立てなきゃ」と身構えるとハードルが高く感じてしまいます。
まずは面白いと思えることから試す。
そこから「自分の相棒」として活用できる感覚を身につけていくことが、これからの時代の経営者に必要なスタンスだと感じました。
-
 生活もビジネスも効率化!今日から始める生成AI活用アイデア
「毎日忙しくて時間が足りない…」家事・育児・仕事に追われながらも、スキルアップも諦めたくない――そんな女性にこ
生活もビジネスも効率化!今日から始める生成AI活用アイデア
「毎日忙しくて時間が足りない…」家事・育児・仕事に追われながらも、スキルアップも諦めたくない――そんな女性にこ
-
 就職活動中のママ必見!生成AIで効率的に自己分析・自己PRする方法
ただいま、高槻マザーズサポートセンター(ハローワーク茨木)で開催される 就職活動中のママ向けAIセミナー の準
就職活動中のママ必見!生成AIで効率的に自己分析・自己PRする方法
ただいま、高槻マザーズサポートセンター(ハローワーク茨木)で開催される 就職活動中のママ向けAIセミナー の準
-
 自分の得意で副業をはじめた!
久しぶりに、わくらくで働いていた橘さんがオフィスに来てくれました!(今でもわくらくインスタのリールの動画編集を
自分の得意で副業をはじめた!
久しぶりに、わくらくで働いていた橘さんがオフィスに来てくれました!(今でもわくらくインスタのリールの動画編集を
-
 補助金活用で夢をカタチに!株式会社みみらぼさんで勉強会を開催しました
先日、株式会社みみらぼさん主催の「補助金活用勉強会」で講師をさせていただきました。みみらぼさんは、耳つぼセラピ
補助金活用で夢をカタチに!株式会社みみらぼさんで勉強会を開催しました
先日、株式会社みみらぼさん主催の「補助金活用勉強会」で講師をさせていただきました。みみらぼさんは、耳つぼセラピ
-
 忙しい女性起業家でも合格できた!簿記2級体験記と学びのコツ
昨年、簿記2級に挑戦し、無事に合格しました。「経営者として会社の数字をもっと理解できるようになりたい」という思
忙しい女性起業家でも合格できた!簿記2級体験記と学びのコツ
昨年、簿記2級に挑戦し、無事に合格しました。「経営者として会社の数字をもっと理解できるようになりたい」という思